
時を超えて息づく“創立精神”は
さらなる飛躍への道に続いていく
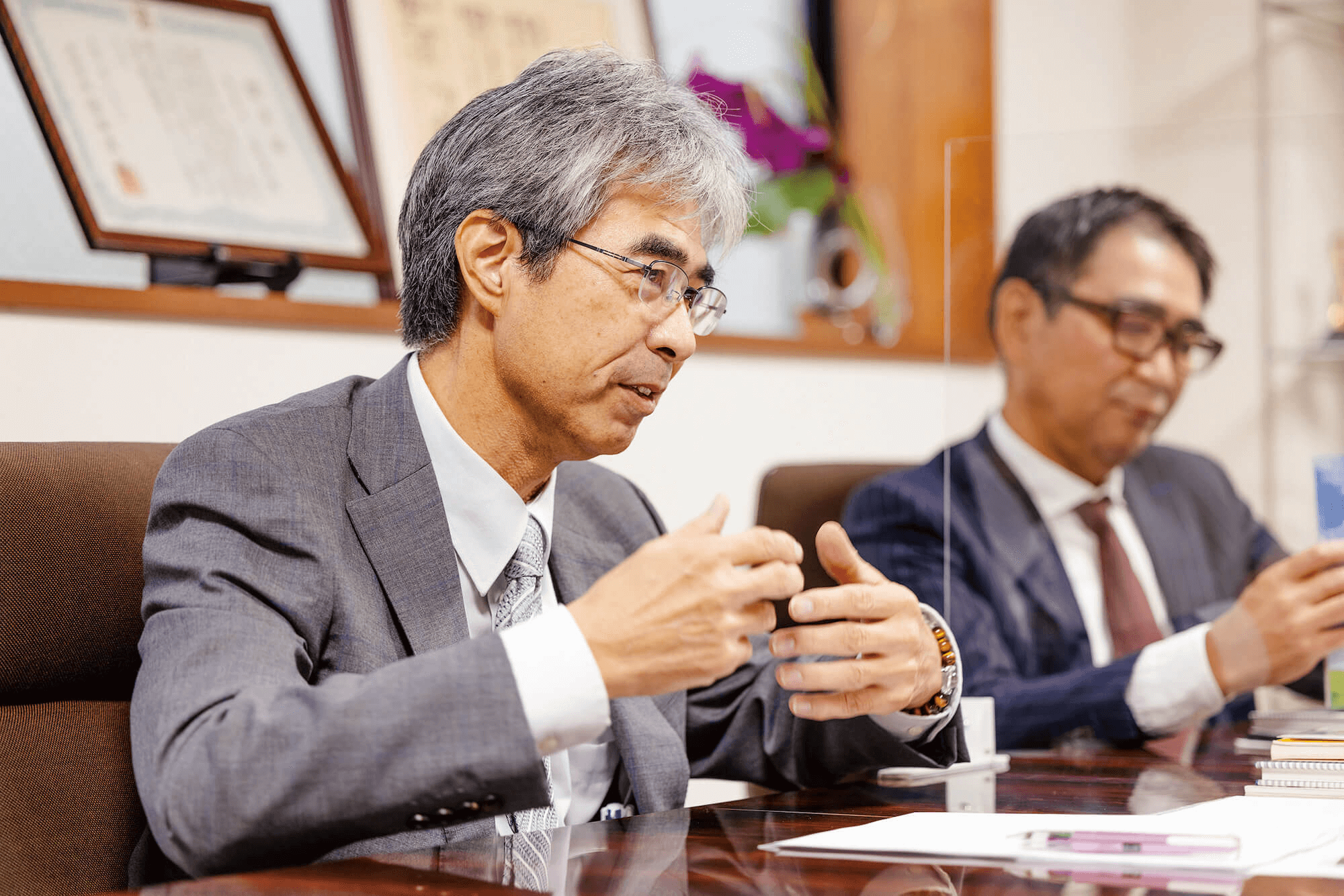
── いち早いチャレンジが自主独立の精神を育んだ
川崎
当社は創業からしばらくは医薬品、それから電子材料とターゲットを広げ、各分野が拮抗しつつ時には外部の力を借りながら、業容を広げてきました。それは自由で風通しのよい社風に加え、さまざまな社員の声をしっかりと拾って形にしてくれる創業者の理解と行動力がなければ成し得なかったと思います。工場にせよ、クリーンルームにせよ、器や環境をいち早く整えていただけたのは大英断だったという他ない。まだ仕事が成立していない段階で、会社としては大変だったはずですが、徐々に器や設備に応じた研究開発の仕事の依頼を受けるようになり、やがてそれが社業の発展を支える技術になっていきました。
荒川
「スタートさせるから、あとは好きなようにやれ」というのが創業者のスタイルでしたね。もちろんその判断が常に正しかったとは言えないかもしれません。ただ、絶えずアンテナを張り、新しいもの新しい領域、新しいヒントを探していた。そしてちょっと興味を持てるものがあるとすぐに見に行く、会いに行く。そうして受ける刺激が創業者自身の、また会社を新しい領域に導く原動力になっていたのだと思います。
土肥
「やってみろ」と信頼して背中を押し、常に社員に最大限の裁量を与えてくれたからこそ、私たちも思いのままに仕事ができました。もちろんその分、各自が背負う責任が大きい厳しさもあるわけですが、それを含めての手応えややりがいが当社で働くモチベーションにもなってきました。経営に携わるようになった今も、そうであると信じています。
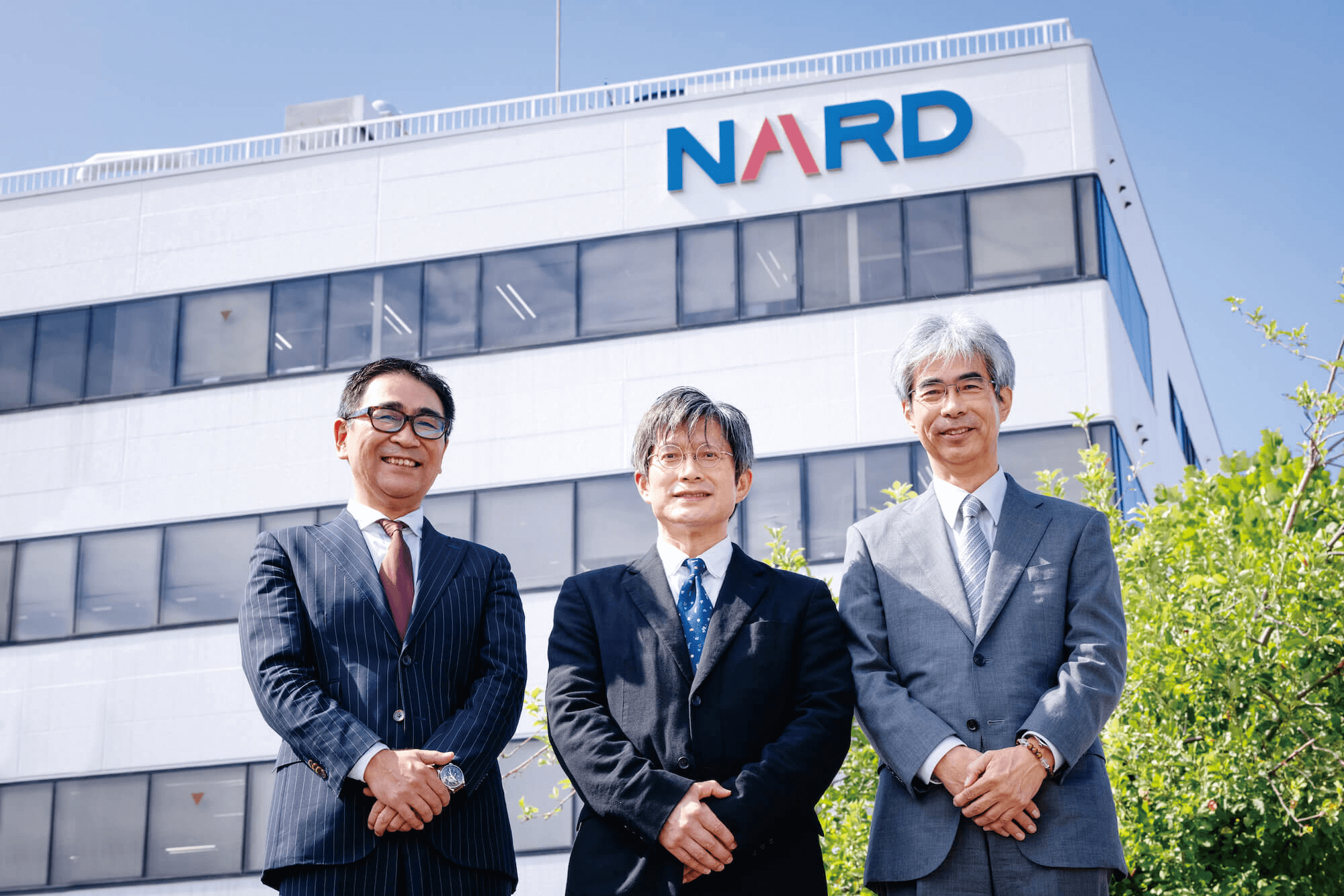
── 「NARDイズム」のもと意識を統一して未来へ
川崎
創業者が体調を崩す90歳くらいまでは誰よりも朝早く出社され、誰かれともなく話をされていた姿が思い出されます。
荒川
とにかくキャラが濃かった(笑)。その存在感、空気感から伝わる強い思いがありました。今はまだ、リーダーをはじめ直に接した経験のある社員がたくさんいますが、これから先、創業者のパーソナリティを通じて受け取ってきた思いをどのように伝えていけばいいのか、悩めるところです。
土肥
その意味ではまだ理念として浸透しきれていない部分もあると感じていますので、言葉で伝えることはもちろん、組織の風土、文化として今以上に実感をもって伝え根づかせていくことがこれからの課題ですね。ちなみにみなさんにとって「NARDイズム」とは何でしょう。
荒川
やはり自主独立の精神のもとで発揮されるチャレンジ精神と言えるのではないでしょうか。
川崎
そうですね。グループの独立採算制という運営システム、営業から研究、請求まで、すべて各自に委ねられることによって育まれる自主独立の精神は、当社ならではのものでしょう。加えて言うなら、やはり「あきらめない」心でしょうか。私自身、できなかった時の悔しさがあるからこそ、がんばってこられたと思っています。
土肥
私が「NARDイズム」と聞くと鮮明に思い出される出来事があります。今から20年ほど前でしょうか、当時、別部署の先輩社員に同伴して、得意先に研究成果を報告に行くことになっていました。高額な研究費をいただき、納期も遅れている仕事でした。ところが朝一番に新幹線で会うと、徹夜明けで会社から駆けつけた先輩社員は開口一番、「できていない。一緒に頭を下げてくれ」と悔しさをにじませている。どうなることかと思いながら分厚い報告書を携えてお客さまのもとを訪れ、できる限りのことをしたが目的物はできなかったという報告をしたんですね。するとすべてを聴き終わったお客さまがひとこと、「いいよ。次に行こう。〇〇さんにできないものは世の中に存在し得ないものなんだよ。」と言ってくださって。心が震えましたね。そこには、技術者と技術者、一瞬で通じ合うものがありました。ともに困難を乗り越え目標に向かう同志として、長いおつきあいの中で育まれたパートナーシップ。これが我々の企業価値、NARDイズムかと、誇らしくも思えました。まあこの話では、そんなふうに言ってくださったお客さまの器が大きくて一番素晴らしいという結論ですが(笑)。
荒川
まったくフラットな状態からそこまで信頼を積み上げていく努力をすることこそが、ナードのナードたる所以ではないでしょうか。
川崎
自主独立の精神で一人ひとりの能力を磨きつつ、あくまで仕事として社会と折り合いをつけ、潜在的なお客さまとどう交流していくか、ニーズをいかに汲み取って社業に取り入れていくのかをみんなが考えてきた会社なんですよね。結果、創業当時は想像もしなかった技術領域、分野でも業績を伸ばしてこられたのだと思います。
土肥
世の中は急速に進展し、求められる技術も多様化の一途をたどっていて、よりレベルの高い技術を身につけていないとどうにもならないことが増えています。反面、先を見通すのは困難で、これをやっていたら安泰ということがありません。活路を開くのは、各自が専門性を継続して伸ばし続けることをベースにしながら、視野を広げ情報収集を怠らずにやっていく、それをもとに意思決定していく。地道ながらもそれを繰り返すことだと思います。
荒川
結局は、創立精神に立ち返ってゆくのだと思います。
川崎
これを根幹として、世代を超えたコミュニケーションができるといいですね。
土肥
何かとスピードが求められる時代ではありますが、特に若い人には、豊富な体験を積むとともに、それを掘り下げて考える時間を持ってほしい。それがNARDイズムを身につけることであり、次代のナード研究所を発展に導く力になっていくと思います。
